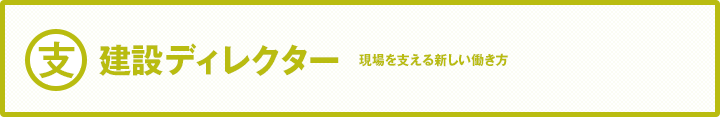2024/06/03
「建設ディレクター課」を創設
ベテラン技術者の、
技能労働者への配置転換求める声がきっかけ
海老根建設(茨城県久慈郡大子町)
建設現場でASP(情報共有システム)や遠隔臨場などICT関連の新しい取り組みが活発になる一方、それに戸惑いを感じる技術者も少なくない。海老根建設株式会社(茨城県久慈郡大子町)でも、ベテランの技術者のそうした新技術等の対応への不安から、現場監理ではなく、技能労働者に配置転換してほしいという声もあったとのこと。そうした声をきっかけに、令和5年度に「建設ディレクター課」を創設。現在、10代から60代までの幅広い年齢層の男女6人が活躍している。「書類作成の業務が昼間に終わり、定時退社や直帰までもできるようになった」などと現場技術者からの評判は上々。社内では略して「KD課」と呼ばれるほど、技術者にとってなくてはならない存在になりつつある。今回は、リモートワークを主としながら、創設当初から建設ディレクター育成にも携わる課長の鈴木由美さんと、異業種から転職した山田美樹さん、高校卒業後に新卒の建設ディレクターとして入社した後藤ひなのさん、いずれも建設ディレクター歴2年目のお二人にお話をお聞きしました。
これまでのキャリアと、建設ディレクターを選んだきっかけを教えてください。
山田:もともと、他の建設会社で経理の派遣の仕事をしていました。私自身は工事の技術的な内容に関する書類作成には携わりませんでしたが、夕方以降に、書類作成に追われる技術者の姿が印象に残っています。その会社の契約満了に伴い、旅行会社の事務職に就きましたが、新型コロナウイルス感染症拡大の影響で観光産業が大きなダメージを受けたこともあって退職し、令和5年に建設ディレクターを募集していた当社に入社しました。建設ディレクターという仕事が、現場を支えるための、パソコンを駆使するオフィス業務がメインというところに興味を持ちました。一度は異業種に身を置きましたが、やはりどこかで、土木のダイナミックさ、魅力を忘れられなかったということですね。道路など、100年先まで使ってもらえる土木構造物を造ることに携われることは、非常にやりがいがあります。
後藤:地元の高校の総合学科を卒業後、「誰かのために働きたい」と、もともとは介護職を志望していました。求人案内で「建設ディレクター(工事事務)」という名称を見て、「素敵な名前だな」と興味を持ち、すぐにインターネットで検索して応募しました。
鈴木:以前は「施工管理補助」で募集しても、ほぼ応募がありませんでした。工事の膨大な書類を現場担当者の代わりに入力・整理するというサポート業務ですが、「建設ディレクター」という名称をつけることで印象が変わり、若い世代の心にも訴えることができたのかもしれません。建設ディレクター課では、この二人以外にも、サービス業で勤務していた方など様々な職歴を持つ方が活躍しています。
いま、どんな仕事をされていますか。
山田:安全書類の作成や確認、工事写真の撮影などに携わるだけでなく、竣工検査にも立ち会っています。着工から竣工までの一連の流れが分からなければ、何の書類をどの段階で作ればよいか分かりません。会社として、一つの現場に建設ディレクターが一人ずつ補助として入る体制をつくっているので、その中で時間をかけてひと通りの流れを覚えているところです。現場代理人に呼ばれて現場に行くこともあれば、月に一度程度、現場パトロールに同行したりします。その時に発生する書類作成業務にもあたっています。
後藤:入社後にドローンの操縦資格を取得したこともあり、ドローンで計測した点群データの処理や3次元測量データの作成などにも取り組み始めました。わかること、できることが増え、日々どんどん世界が広がっています。
鈴木:建設ディレクター課の課長として、主にリモート勤務をしながら、工事を担当する管理課と建設ディレクター課の間の調整、指示を行っています。建設ディレクターの育成、マネジメント、工事書類全般の管理を担当しています。
仕事の楽しさは
後藤:建設業に対する3K(きつい、きたない、危険)のイメージが、入社前には正直ありましたが、実際に働いてみると、本当に現場の皆さんが家族のようで、業界に対するイメージが180度がらりと変わりました。モノができていく喜びが想像以上に大きく、毎日〝誰かのために〟を意識して、楽しく働いています。
山田:現場代理人からのリクエストで、舗装を施工する現場の材料確認などのお手伝いをした道路が開通したとき、自分自身で、車で実際に走ると「すごいな」と感動します。大げさな言葉ではなく、現場の技術者のみなさんからの「ありがとう!」「助かった」という言葉で、自分が役に立つモノを造ることに貢献していると感じることが何よりも支えになっています。皆さんから感謝されると、少しは「縁の下の力持ち」に近づけたかもしれないと、思わずガッツポーズになります。
鈴木:パソコン作業も多くなる中で、年配の技術者ほど「苦手意識があるから丸ごと任せる」などと、(建設ディレクターの存在を)頼りにしてくれています。またこれは年配、若手に関わらず、「現場から戻ってきて、夕方から書類作成をスタートするという状況がほぼなくなり、明らかに残業時間が減って助かっている」との声もあります。
困りごとや工夫は
鈴木:一番難しいのは、現場監督の方の意識を変えることですね。皆さん決して「自分の仕事を任せたくない」と考えているわけではありません。「本当は誰かにやってもらいたいけど、教える時間がない」のが本音。「自分なら1、2時間で終わるけれど、任せるとなれば、確認をするのに半日は必要」と考えるからです。それでも「少し長い目で見て、徐々に任せてもらえませんか」と話して、少しずつ任せてもらえるように調整しています。現場の書類作成に精通するベテランが、リタイア後に指導教官のようになってもらえれば一番よいと思います。
鈴木:現在、一つの現場で作成が必要な書類業務約250項目を抽出した上で、どの仕事を建設ディレクターに任せるのがよいか検討した上で、統一マニュアルを作成している最中です。マニュアルがあれば、チーム全体で業務のサポートができ、効率化や無駄な工程のカット、残業減にもつながります。「建設ディレクターの初心者でも、これを見れば一定程度の書類ができる」というものにするのが目標です。
技術者とのコミュニケーションを円滑にするための工夫は?
鈴木:お二人の入社を機に、社内のデスクの配置を大幅に見直しました。フロアの中央に建設ディレクター課の机を置き、それを取り囲む壁側を、現場の技術者が作業するフリースペースにしました。技術者にとっては、現場から戻ってどこに座っても、振り向けばすぐ建設ディレクターがいて、気軽に話しかけることができる狙いがあります。建設ディレクター課を別室にしてしまうと、途端にドア一枚が分厚い〝壁〟になってしまい、それをノックして入室するという勇気が出ない方も、もちろんおられますから。
山田:技術者の方から、現場から直接、ビジネスチャットツール「LINE WORKS」で指示をくれるのがうれしいですね。現場と事務所と離れていても、トーク画面で気軽にやりとりしています。LINEと操作性が近いので、私も技術者の方もスムーズに使えています。
後藤:先週、山田さんと一緒に、社屋の一角にミニトマトの苗を植えました。夏の熱中症予防に備えて。うまく実るか楽しみです。技術者の方ともそうした何気ない話題で会話が弾むことで、親近感が強まって、仕事の話も気軽にできるような気がしています。
建設ディレクターを選んでよかったこと
後藤:同じ空間で対話ができるのがベストだと思いますが、書類作成やデータ処理も、スキルを身につければいずれリモートでどこででもできるようになります。将来を見通した時、主婦層や子育て世代でも柔軟に働き続けられる職業に建設ディレクターはなっていくのではないでしょうか。
山田:近い将来、親の介護が必要となることを考えれば、リモートワークができることに安心感があります。建設ディレクターの仕事に出会えて、心底よかったと思っています。
今後の目標、夢は
山田:竣工検査など、普段の生活では経験できないことの連続ですが、それを楽しいと思う気持ちが大事。車で走ると、景色の中にたくさんの建設構造物があり、それらをつくる仕事に携われる達成感を感じることができます。「人に尋ねずに出来るようになりたい」「新しいことを覚えていきたい」「どんな形で法面(や舗装)ができるのか見てみたい」という好奇心が、私の原動力になっています。現状に満足せず、ゆくゆくは施工管理技士の資格にも挑戦したいですね。
後藤:三次元測量のスペシャリスト、また、現場マネジメントのできる、かっこいい現場監督になりたいと思います。
建設ディレクターにはどんな人が向きますか。興味のある人にアドバイスを。
後藤:三次元データ作成はデジタルに興味があり、その扱いに慣れている、デジタルが好きという私のような世代、デジタルネイティブにぴったりだと思います。最近では高校でもドローンの授業があり、操縦資格をもっている学生も多いので、デジタル好きの若い人はぜひ一度、体験してほしいですね。
山田:特別なスキルや専門知識がなくても、入社後の研修や建設ディレクター協会の認定講座で、建設業の書類作成業務に不可欠な基礎知識、現場とのコミュニケーションスキルも学べます。「縁の下の力持ち」の面があるので、とにかく現場代理人に依頼されたら積極的に取り組んでみる。それが知識や経験につながるのだと思います。積極的で好奇心旺盛な方は特に向いていると思います。
おわりに
異業種から転職した山田さん、建設業とはほど遠い業界を志望していたという新卒入社の後藤さん。年齢は異なるお二人ではありますが、ともに建設ディレクターとしての工事書類作成を通じて建設業に魅力を感じ、「かっこいい現場監督になりたい」など、将来的には現場への配置転換までも思い描いていることが印象的でした。もともと同社は、デジタルに苦手意識をもったベテラン技術者が「技能労働者に配置転換を」と声をあげ、そうした技術者の〝長寿命化〟を見据えた環境づくりの一環として建設ディレクターを導入したそうですが、想定以上の好循環をもたらそうとしています。
技術者の確保は各社共通の課題ですが、この新しい職域が、建設業への間口を広げていくきっかけとなることを確信しました。
現場の失敗と対策
- 2026/02/02
- 基礎工事 3)既製杭 根固め部の施工不良による支持力不足
インフラ温故知新
- 2026/02/02
- vol.7 大阪と日本のインフラ 炭鉱
今月の一冊

-
2026/02/02
『桃太郎がやってくる ~どうなる鬼ヶ島⁉~』
土木・建築、独自開発のパワーブレンダー工法による地盤改良事業などを手掛ける加藤建設(愛知県蟹江町)が、「建設業をあこがれの職業No.1へ」との思いで、社員のアイデアを形にした...
Copyright © 2013 一般財団法人 建設業技術者センター All rights reserved.